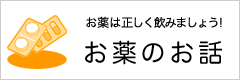第1話「薬のかたち」
“ 薬のかたち”は効用を活かすために
飲み薬や塗り薬、湿布、注射に点滴。
飲み薬にも、散剤、錠剤、カプセル、シロップなどなど―――。
「薬」とひとくちに言っても、いろいろな形があります。その理由は、薬をより効果的に効かせるためです。この “薬のかたち”のことを「剤形」といいます。
私たちが自分で用いることのできる薬は、主に内服薬、外用薬の2タイプです。代表的な剤形と特徴、効果などについて見てみましょう。
かたちで異なる薬のはたらき
内服薬(飲み薬)
飲み薬の多くは主に小腸で吸収され、全身に効果を及ぼします。
- 散剤
- 粉末状の飲み薬は、溶けやすく、吸収が早い薬です。このタイプは細かい分量の調整がしやすく、体の小さな 子ども用にも多く処方されます。
- 錠剤
- 粉末を固めた錠剤は、保存性が高く、持ち運びにも便利。錠剤に特殊な加工を行うことにより、長時間効果が持続する錠剤や、唾液ですぐ溶けて水なしでも服用できる錠剤もあります。
- カプセル剤
- カプセルは、においがきつい薬用成分や、苦みの強い薬用成分を包みこんでくれます。油状など固めづらい成分にも使われています。
- シロップ剤
- 子ども用に使われることの多い液状の薬で、分量の調整がしやすく、飲みやすい味のものが多いです。ドライシロップと呼ばれる薬は、粉末のままでも飲めますし、水に溶かしてシロップ状にして飲むこともできます。
外用薬(塗り薬・湿布など)
関節や腰、肩の痛みなど、特定の部位への効用が主な目的です。目や口内炎用の塗り薬もあります。特定の部位に適量を用いることができるので、副作用も抑えることができます。
“変わって”も、“変えて”はいけない
現代では、あまり見られなくなった剤形もあります。代表例は、生薬を煮出す煎じ薬。いまでも販売されていますが、多くは粉末・顆粒状へとかたちを変えました。
しかし、“薬のかたち”を自己判断で変えることは、避けたほうがよいでしょう。錠剤を削ったり、カプセルを割って中身を取り出したりすると、 薬の効き方が変わってしまうことがあります。医師や薬剤師の指導を守り、処方を受けたご本人のみが用いるようにしてください。
手稲渓仁会病院 薬剤部