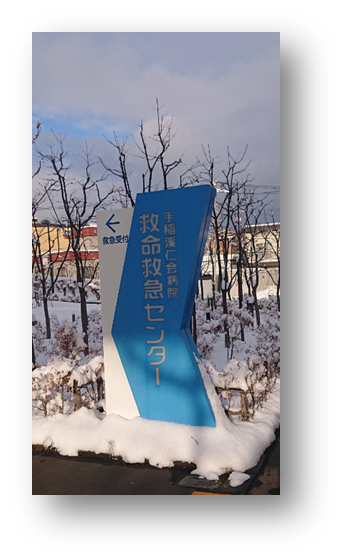こんにちは。2年目初期研修医の志村と申します。
寺田先生の記事にもありましたように、当院では国内外を問わず他施設での院外研修が可能です。私はニュージーランドのホスピスで4日間の研修をさせていただきましたので簡単にご紹介します。
北島の都市、ウェリントンの郊外にTe Omanga Hospiceは位置しています。ニュージーランドでは、多くの方が自宅で最期の時間を過ごすことを望み、それを実現しています。Te Omanga Hospiceは、外来・入院・在宅での緩和ケアを行なっている施設で、年間320人の患者さんを看取っているそうです。
ベッドは8床あり、終の住処というよりも、一次的に症状コントロールを行うための病棟としての役割が大きいことが特徴です。ホスピスで亡くなる方もいらっしゃいますが、多くの患者さんが入院中に症状コントロールを行いながら、家族会議を重ね、準備を整えて自宅へ戻って行きます。
家族会議は、本人、家族、医師、看護師、ソーシャルワーカーで大きな輪を組み、現状や今後の方針について共有する場です。一度、マオリ族の腎不全患者さんの家族会議に参加させていただきました。まず皆で祈りを捧げるところから始まり、現在の症状や今後などについてじっくりと話し合った後、皆で肩を組んで歌を歌い会議を終えました。会議自体はシビアな内容も含まれ、途中家族が涙する様子もあったものの、最後には皆、笑顔で前向きな発言をする様子が多くみられていました。
愛する者との別れは辛く悲しいものです。しかし、時間が限られているからこそ、命はより輝き、大切な時間を過ごすことができるのではと感じました。ニュージーランドの雄大な自然に囲まれ、優しい時間が流れるホスピスで、私自身が豊かな時間を過ごすことが出来ました。
日常とは全く異なる環境に飛び込み、新たな気づきを得られることが院外研修の醍醐味ではないでしょうか。院外研修を行うにあたり、お世話になった皆様にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

Te Omanga Hospice, located in Lower Hutt, in the North Island of New Zealand provides inpatient, outpatient, and home-based palliative care. Thanks to the doctors and medical staff at both TKH and Te Omanga Hospice, I had the opportunity to visit there on an elective.
Te Omanga Hospice has eight beds for patients who need acute symptom control or for terminal care but these days, many patients prefer to spend as much time, and ideally the end of their life in their own home.
Family meetings play a vital role to achieve good quality of life for patients with terminal illness. I attended one of these family meetings for a Maori patient – it started with a Karakia, a prayer in the patient’s native language. After the prayer, we discussed the present situation, the patient’s goals and likely future prospects. We discussed what was needed for him, what could be provided and then set goals together. At the end of the meeting, we sang a song putting our arms around each other’s shoulders.
Being separated from a loved one is never easy. However, they remind us of how precious life is. They teach us to live as if each moment is a gift. Dying is a normal process. Death is necessary for our life to be meaningful. The days I spent at Te Omanga Hospice were some of the most peaceful and serene of my life and made me realize the essential things in life.