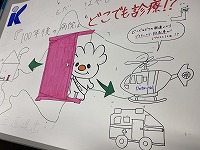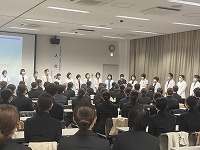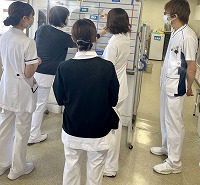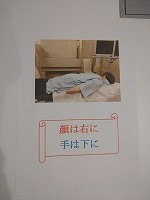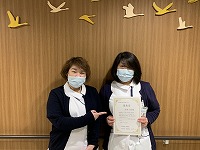コロナ禍の生活になり早3年目になりました!
当院も感染に注意しながら日々スタッフ同士協力して業務に励んでいます!
そんな中、時には息抜きが必要とのことで
今回は、日々の業務に少し休日のプライベート姿をお見せしようと思います!
私たちの部署では、ホワイトボードを使用して皆の業務を可視化し、
定時で業務を終了できるようにお互いに声を掛け合っています。
そのため、ナースステーションでは常にスタッフ同士の声が飛び交っています(笑)
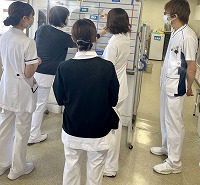

そんな多忙の中の休日には…
それぞれ好きなことをして過ごしています。
釣りを趣味にしているスタッフも多く、どこで○○が釣れる~、ここで○○を釣った~
などの会話が飛び交うことも(^_^)



仕事から離れ、仕事とはまた違う顔!!(笑)
それぞれ息抜きをしています!!
このご時世で家に引きこもることばかりで精神的にも辛いですよね
気持ちが暗くなる、何もしたくなくなる
趣味があると心が明るくなり前向きな気持ちも生まれやすくなります!
コロナ禍になって趣味をもつ人が増えてきたようなので、ランキングでお伝えします!
1位・・・キャンプ、アウトドア、登山
2位・・・釣り
3位・・・園芸、家庭菜園 などなど
外で行えることが多くランクインしているようでした!!!(ネット調べ)




趣味がないなぁ…って方は、興味をもてるものを見つけてみるのも良いかもしれないですね!
それだけでワクワクしてきませんか??
コロナも感染の波が何度も訪れていますが、上手く付き合い感染予防して、
息抜きを挟みながら、一緒に頑張って行きましょうね!!(*^_^*)