こんにちは!
B6病棟の入院患者さんはご高齢の方が多いため、
身体の回復プロセスを支えながら
機能を維持することができるよう支援しています。
今年度は2名の新人看護師と、
グループ病院から1名のスタッフが仲間入りしました。


4月は研修を受けたり、
先輩看護師のシャドウイングなど経験しました。
点滴を混注する先輩の姿を後ろからそっと見つつ・・・

そして、今度は見守られつつ自分たちで混注しています。

そんな病棟の混注室には大きな窓があり、
外の様子を感じられる気持ちの良い空間になっています。
院内や部署内で様々な研修を行っていますが、
その一つとして助手業務を体験しました。

助手さんは関連部署と連携をとりつつ、
メッセンジャーとして病院内をラウンドしています。
メッセンジャー業務の合間には病棟の環境整備も行ってくれており、
「陰で助手さんが色々やってくれていることを知れた」と、
気づきが得られたようです。
また、看護師を含む多職種との連携だけではなく、
当院のどこにどのような部署があるのかもある知ることができました。
ゴールデンウィーク明けから、患者を受け持ち始めました!!
緊張のなか、リーダーと今日の予定を確認してきます。

これから今まで経験したことがないたくさんのことを経験し、
成長していく様子を病棟スタッフみんなで見守っていきたいと思います。












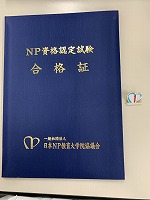










 <A棟:モチーフ鳥>
<A棟:モチーフ鳥> <B棟:モチーフ花>
<B棟:モチーフ花> <F棟:モチーフ葉>
<F棟:モチーフ葉>








